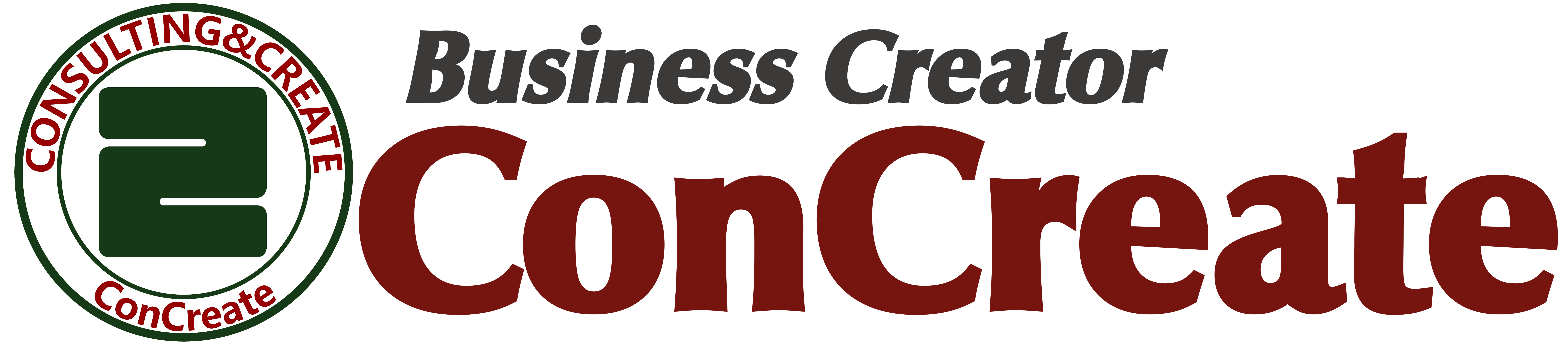なぜ若手社員には「常識」が通じないのか?

「社員教育にこれほど悩まされるとは思わなかった…」
これは、ある飲食店経営者の言葉です。
売上を伸ばすための戦略や商品力には自信がある。
けれど、人材育成だけがどうしてもうまくいかない。
特に問題なのは、「若手社員に何を言っても伝わらない」という現実です。
さらに彼らが異性であれば、価値観の違いによる“見えない壁”はさらに高くなります。
◆社員教育の現場で起きている3つの構造的問題
あなたの会社でも、こんなことが起きていませんか?
- 注意しても「不機嫌になる」か「聞いていない」
- フレンドリーな接客を求めたら、タメ口・馴れ馴れしさで逆効果
- あいさつ・敬語・礼儀といった“常識”が伝わらない
これは個人の性格の問題ではありません。
今、企業の現場で起きている社員教育の問題は、次の3つの構造的課題によって引き起こされています。
【1】世代間ギャップによる“常識の分断”
昭和・平成世代が「社会人として当然」と思ってきた価値観は、令和の若手には通用しません。
たとえば…
- 「目上の人に敬語を使うのは当たり前」→「仲良くなるためにフランクな方がいい」
- 「お客様は神様」→「過剰にへりくだるのは違和感」
このような価値観の違いを前提にしない教育は、最初から破綻しているのです。
【2】「指導=命令」と誤解している教育スタイル
経営者や上司が「正しいことを教えているのに反発される」と感じている場合、その“教え方”が一方的な命令・矯正型になっていないかを見直す必要があります。
今の若手は、「納得できないことは受け入れない」世代です。
背景・理由・意味を伝えずに「こうしろ」と言えば、拒絶反応を示すのは自然な反応とも言えます。
【3】“フレンドリー”と“無礼”の境界線が曖昧
最も現場で困るのがこの部分です。
「親しみやすい接客でいいよ」と言ったら、言葉遣いが崩れたり、態度がフランクすぎてクレームに。
本人は良かれと思ってやっているため、注意すると逆ギレされるケースもあります。
ここにあるのは、社会通念(常識)と本人の感覚の乖離です。
◆では、経営者はどうすればいいのか?
社員教育を成功させるには、次のような“教育の再定義”が必要です。
【STEP1】「価値観が違って当然」と受け入れる
まず前提として、若手社員の価値観が自分と違うことを“異常”と捉えないこと。
「なぜ理解できないんだ?」とイライラする前に、“違い”を前提に教育設計をすることが唯一の突破口になります。
【STEP2】常識を“言語化”し、行動レベルに落とし込む
「そんなの社会人ならわかるだろう」は通じません。
あいさつの声量・距離感・敬語の使い方・接客時の態度…
曖昧な“感じ方”を具体的な“行動レベル”にまで落とし込んで伝える必要があります。
例:
「もっと丁寧にして」→✕
「語尾まで言い切る。語尾を伸ばさない」→◎
【STEP3】“納得”をベースにした指導を行う
「こうした方がいい」ではなく、「なぜこれをするとお客様に喜ばれるのか?」
「どんなリスクがあるのか?」といった背景まで共有することで、若手は動きやすくなります。
◆教育の質が変われば、会社の未来が変わる
社員教育はコストでも手間でもありません。
正しく行えば、最も費用対効果が高く、組織力を一変させる“成長投資”です。
教育が変われば…
- 接客の質が改善し、クレームが減る
- 若手が辞めなくなり、人材定着が進む
- 経営者のイライラ・疲労感が激減する
- 社員が自発的に動き、経営に余裕が生まれる
こうした「目に見える効果」が、確実に現れます。
◆まとめ:社員教育に“正解”はない。だが、“設計”はできる
これからの社員教育に必要なのは、自分の経験を押しつけることではなく、構造的に“教え方”をデザインする力です。
価値観ギャップを嘆くのではなく、「どう伝えるか」「どう理解させるか」にシフトする。
それが、教育に悩むすべての経営者に求められる意識改革です。
このブログの内容をもっと詳しく知りたい方は、無料メルマガ登録をお願いします。
メルマガではテーマを決めて、その解決案を7日間の連続メールで解説しています!
無料メルマガ登録はこちら↓
https://utage-system.com/p/fRML0lKBE3cG